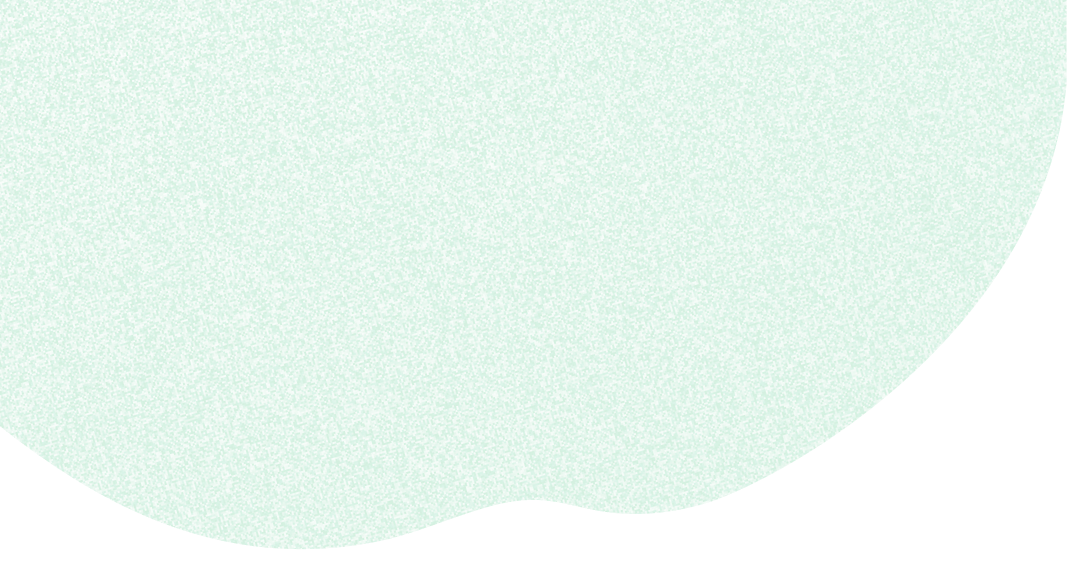生成 AI プロンプトエンジニア検定受験体験記
はじめに
こんにちは。株式会社イースト・コースト・ワン、第一技術部の鈴木です。私は普段ウェブシステムの開発を行っています。最近は、私の職場でも「生成 AI をシステムに利活用できないか」といった話題が上がることが増えてきました。
生成AI(Generative AI)とは、文章や画像、音声、動画などを命令に応じて作り出してくれる人工知能技術です。入力した質問に回答を返してくれる「ChatGPT」や、入力した説明文に応じた絵を自動で生成してくれる「DALL·E」などが有名です。これら生成AIは、大量の情報をもとに学習し、メールの文案を考えたり、アイデアのブラッシュアップを手伝ってくれたり、データ分析のようなことを自動でやってくれたりと、ビジネスの現場でも活躍の場がどんどん広がっている技術です。
今回は、私が取得した 生成AI 関連資格である「生成 AI プロンプトエンジニア検定」について、その内容や、合格するまでに実践した勉強方法などをご紹介いたします。
生成 AI プロンプトエンジニア検定とは
この検定は、生成 AI プロンプト研究所(https://chapro.jp/)が実施しているもので、生成 AI に対して適切な指示(プロンプト)を入力するための基礎知識を身につけ、より精度の高い回答を引き出す力を養うことを目的とした検定です。その名の通り、「生成 AI にどう指示(プロンプト)を出すか」にフォーカスした内容となっており、実践的な活用スキルを学ぶことができます。
私自身、プログラマとして生成 AI そのものを開発することにはもちろん関心があるのですが、まずはユーザーとして生成 AI を有効活用するための知識を身につけ、また日々の業務効率を高める使い方も学びたいという思いから、この検定の学習に取り組むことにしました。
受験方法・テキスト
検定試験は、生成 AI プロンプト研究所の公式サイトからオンラインで受験することができます。テキスト購入から受験までの流れは以下のようになります。
- Amazon にてテキストを購入 : 生成AIプロンプトエンジニア検定 [改訂版]2025年度版 公式テキスト&問題集
- テキストを読み込んで勉強!
- テキスト内に記載された専用コードを確認
- 生成 AI プロンプト研究所の公式サイトで会員登録
- 会員登録後、マイページにて専用コードを入力して、試験を受験
この検定は、受験料が公式テキストの価格に含まれているという少し特殊な形式となっており、テキストに記載されている検定受験のための専用コードを使用して申し込む仕組みです。そのため、本屋さんなどで立ち読みしてコードだけを取得されることを防ぐ目的からか、公式テキストは書店にはまず置いておらず、Amazon を通じて購入する必要があります。私は最初この仕組みに気づかず、いくつかの本屋さんを梯子しては「なぜどこにもないのだろう?」と不思議に感じていました。これから受験を検討されている方には、この点にご注意いただければと思います。
検定で問われる知識と難易度
この検定では、以下のような分野の知識を問われます。(公式テキストの目次から抜粋)
- 生成 AI カリキュラムについて
- 生成 AI についての基本的知識
- 実践的なツールと使用方法
- 「プロンプト 8+1 の公式」について
- 覚えておきたい知識と注意点
生成 AI に関する基本知識に加えて、より的確で効率的な回答を得るためにはどのような要素をプロンプトに含める必要があるか、といった実践的な内容も問われます。難易度は基本レベルでそれほど難しくはありませんでした。また、ここで得られる知識は特定のサービスやツールに依存したものではありません。一般的な生成 AI に対して広く活用できる知識となっている点も大きな魅力です。
実際の勉強方法と勉強時間
学習には公式テキストのみを使用しましたが、それだけで十分試験対策ができるように作られていました。基礎知識についてはテキストを繰り返し読み込むことで理解を深め、プロンプトの書き方については公式テキストに掲載されている具体例やテクニックを実際に ChatGPT に入力して結果を確認するという実践的な方法で学習を進めました。公式テキストの後半には問題集が収録されており、自分の理解度を確認しながら繰り返し学習できる構成になっています。私の場合は、全ての問題に正解できるようになるまで 3 周ほど繰り返し解きました。勉強に費やした時間は、トータルでおおよそ 10 時間ほどだったかと思います。
学習してみて特に「これは使える!」と感じたのは、「プロンプト 8+1 の公式」です。これは、生成AIからの回答の質を最大化するためのテクニックとして、8個の情報+1つの追加指示を活用するというものです。その内訳は、
- 前提条件 : 何をしたいのか回答の目的と目標を記載
- 対象プロファイル : 誰宛ての回答なのかを提示
- 参考情報 : 回答を生成するための背景情報を示す
- 名刺と動詞 : 何をしてほしいかを名刺と動詞を使って指示(〇〇を△△してください)
- 形容詞 : ポイント4に対して、「どのような」を追加して精度を上げる
- 出力形式 : 回答の形式を文字ベースで指定する(「メール形式」「Q&A形式」など)
- 参考フォーマット : ポイント6に加え、回答の形式や構造を指定する(「大事な点は太字にする」など)
- 文体指定 : 回答のスタイルやトーンを指定(「ビジネス文書風」や、「会話風」など)
そして、
- 追加指示 : 再度指示することで精度が上がる、出力を見ながらフィードバックを繰り返す(「具体例を挙げてください」、「別視点からの意見を提供してください」、「(特定の部分について)もっと詳しく」など)
の合計9項目です。これらは、毎回全てを指定しなければいけないわけではありません。必要な情報をプロンプトに組み込むことで、曖昧な指示から、的確で再現性のあるプロンプトを設計できるようになります。特に業務での活用や教育、ライティングなどで効果を発揮します。
試験内容
試験は全100問で、いずれも4つの選択肢の中から正解を選ぶ形式です。私が受けた試験では、問題はすべてテキスト内に答えがあるものばかりでした。検定は自宅からオンラインで受けることができ、カメラをオンにするなどの制約もないため、実際には試験中にテキストを参照することも可能です。
とはいえ、問題数が多いため、一問ずつテキストを確認していると時間が足りなくなる恐れがあります。あらかじめ公式テキストでしっかりと勉強しておくことで、余裕を持って回答を進められるでしょう。
合格後
試験の合否結果は、受験後すぐに確認することができます。しかし、合格後に正式な認定を受けるためには、もう一段階手続きが必要です。それは、「公式テキストを手に持った状態の写真を撮影し、運営元へ送る」ことです(※顔の一部が隠れていたり、多少不鮮明であっても問題ないとのことです)。実際に私はマスクを着用したままの写真を提出しましたが、問題なく認定を受けることができました。正直なところ、写真を送るのは少し抵抗がありましたが、テキストに受験料が含まれているため、その確認の一環として必要なのではないかと考えています。
写真を送付すると、運営元での確認が完了し次第、合格証書がPNG形式の画像ファイルとしてメールで送付されてきます。私の場合は、月曜日の夜に写真を送ってから木曜日の夜に認定証が届きました。この合格証書は、SNSのプロフィールや名刺、ホームページなどで「生成AIプロンプトの知識を有していること」の証明として活用することができるとのことです。AIを取り巻く環境が急速に変化する今、この認定証は「生成AIを活用できます」と自信を持って伝えられる、証明書になるでしょう。
まとめ
ChatGPT をはじめとする生成 AI は、たとえ質問の仕方が多少曖昧であっても、それなりに意図を汲み取った回答を返してくれるという利便性があります。しかし、今回生成 AI プロンプトエンジニア検定の学習と受験を通じて、適切な指示(プロンプト)を与えることで、そのポテンシャルを最大限に引き出せることを学びました。
実際に私は、自身が開発しているWebシステムのユーザーとメールでやり取りする機会が多く、また開発業務の中ではアメリカ人メンバーとのコミュニケーションも日常的に発生します。そんな時のために、例えば以下のようなプロンプトの雛形をあらかじめ保存しておき、必要に応じてすぐに使えるようにしています。
- ITに詳しくないお客様(対象プロファイル)への返信メールを、丁寧ながらも堅すぎない(文体指定)表現で作成
- 同じチームのアメリカ人メンバー(対象プロファイル)への連絡・作業依頼メールを簡潔な(形容詞)読みやすいアメリカ英語に翻訳
- プログラムのテスト内容を検討する際に、漏れのないテストを設計する(目的)ために、テスト観点(例:正常系・異常系、境界値など)を網羅的にリストアップ
(実際にはもう少し複雑な指定を行なっていますが、それは企業秘密です)
こうしたプロンプトを活用することで「丁寧な文章にして」や、「英語に翻訳して」「テスト条件を列挙して」といったシンプルな指示を出すよりも、より的確でちょうどよい表現が得られるようになったと感じています。これは、プロンプトエンジニア検定の学びを活かして実践している成果のひとつです。
このように、生成AIプロンプトエンジニア検定で得られる知識は、日常の業務や情報収集、アイデアの整理など、さまざまな場面で即戦力として活用できるものです。生成 AI をもっと有効に使いこなしたいとお考えの方や、業務の効率化・創造的な仕事への活用を検討されている方には、この検定の受験を心からおすすめしたいと思います。